墓じまいをすると災いがある?気を付けた方が良いポイントは?

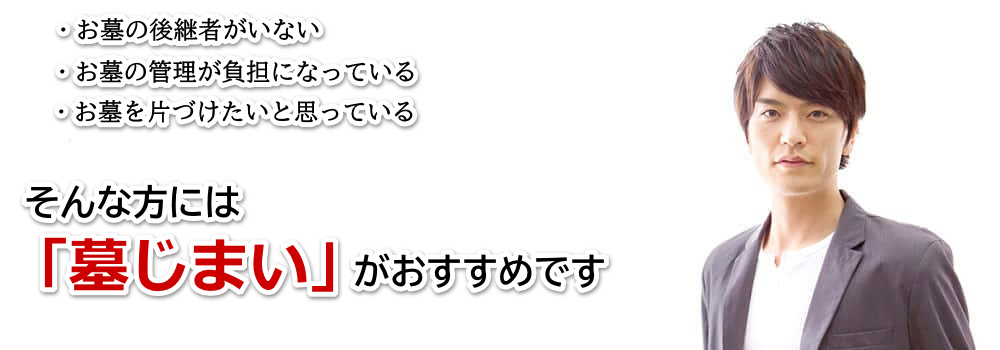
「墓じまいをすると、災いが起こるって聞いたけど、ホントなのかな・・・?」
「墓じまいをしたいけど、災いが怖い・・・」
あなたはこんな事で悩んでいませんか?
確かに、お墓の管理が難しければ、墓じまいを考えるのは自然なことです。
でも、墓じまいをすると災いが起こると聞くと、不安になりますよね。
この記事では、墓じまいをすると災いが起こるのか?について解説していきます。
目次
墓じまいで災いが起こる?
まず、お墓に埋葬するという観点から、仏教である前提で説明を進めていきます。
仏教では人が死ぬとお葬式を行いますが、このお葬式というのは、「故人が無事に極楽浄土にたどり着けますように」という願いを込めて行われるもので、
「故人が祟らないように」という観点から行っているわけではありません。

したがって、亡くなった人はもれなく成仏していると言えますので、お墓を墓じまいして、永代供養に切り替えたところで、ご先祖様が怒って災いが起こる、というのはあり得ないということになります。
実際、お寺のお坊さんに墓じまいについての良し悪しついて尋ねると、宗派によって若干考えが異なるものの、「きちんと供養して改葬していれば問題ない」という答えが返ってきますし、墓じまいが原因でご先祖様が災いを起こす、というのは考えにくいのです。
墓じまいで災いは起こらない!墓じまいのメリットは?
前途の通り、墓じまいをしたからといって、災いがあるというのは、ただの迷信だと思って差し支えありません。
むしろ、墓じまいをして、永代供養に切り替えることで、大きなメリットがあるのです。
ここでは、墓じまいのメリットとデメリットを解説します。
墓じまいのメリット
お墓の管理をお寺に任せることができる
お墓の遠方に住んでいる、高齢である、等の理由から、お墓の管理が負担になっている家庭は少なくありません。
また、お墓によっては、傾斜がきつい、足場が悪い、など、物理的に危険な場所にお墓がある場合もあるでしょう。
そういう場合は、墓じまいをすることで、お墓の管理から解放されるため、肉体的な負担を軽減することができ、お墓にかかる費用なども抑えることが可能です。
先祖が無縁仏にならない
遺族がいないお墓は、無縁仏になることがあります。
また、お墓に管理者がいる場合でも、管理費を滞納している、お墓が荒れ放題になっている、などの理由で、無縁仏として扱われる事例が増えています。
お墓の管理ができない場合は、無縁仏にしてしまうより、墓じまいをしてお寺に管理を任せた方が、ご先祖様の供養に繋がることがあります。
墓じまいのデメリット
撤去にお金がかかる
墓地の解体には、もちろんお金がかかります。
一般的には、撤去費用は墓地の面積や墓石の大きさで決められるため、想像以上に高額な料金になる可能性もあります。
したがって、石材店に墓じまいを依頼する際は、事前に撤去費用について見積もりをとり、よく検討することが重要です。
親族同士やお寺とトラブルになる可能性がある
お寺の檀家である場合は、墓じまいをすることでトラブルになる可能性があります。檀家とは、1つのお寺に所属して供養などお勤めいただくかわりに経済的な支援をすることです。
お寺の運営は檀家の支援で成立しているため、墓じまいして離れることは先方にとって大きな経済的負担となります。
また、新族のなかには墓じまいに対して「罰当たり」「道理に外れている」などという考えを持つ方もいるでしょう。価値観の違いから意見が食い違ってしまう恐れもあります。
お寺の檀家になっている場合は、墓じまいがトラブルになることがあります。
ご存知の通り、お寺は檀家の支援で成立していますので、墓じまいをして檀家を抜けることはお寺側からすると大きな負担になることがあります。
また、親族の中には墓じまいに対して「罰当たり」などの悪いイメージを持っている方もいらっしゃるでしょうから、意見の口違いから思わぬトラブルになる事例も。
こうならないためにも、墓じまいを検討している場合は、お寺や親族間でよく話し合い、全員が納得できる形を選びましょう。
墓じまいで災いを起こさないためにも、スムーズな墓じまいを
墓じまいをしたからといって、災いは起こりません。
しかしながら、いざ墓じまいをしようとして、もたもたしていると、ご先祖様にも失礼ですし、災いに繋ながりそうで不安になりかねません。
そうならないためにも、墓じまいから永代供養をするまでの手順をしっかり把握しておきましょう。

お墓がお寺にあれば、檀家から離れることになりますし、民間墓地にある場合は、管理費等々、様々な弊害が生まれるでしょう。墓じまいは行政機関に基づく正式手続きが必要なのです。
墓じまいは独断で行えることではないため、関係者への周知を怠ることなく、今後も良好な関係を築けるよう、配慮することが大切です。

なお、「改葬許可証」・「申請者の印鑑」などを揃えて、再度役所に提出する必要があります。
墓じまいで災いが起こる?のまとめ
この記事では、墓じまいで災いが起こるのか?について解説しましたが、いかがでしたか?
この記事の内容をまとめると、
・墓じまいで災いが起こることはあり得ない
・災いの心配よりも、スムーズに墓じまいを行えるよう、事前に調べておくことが重要
となります。
お墓を墓じまいして永代供養に切り替えることは、仏教に反することではなく、現代の多様化社会に合わせた新しい供養方法です。
墓じまいには、事前によく調べ、周りに周知し、理解を得ることが大切なポイントになります。
あなたの大切なご先祖様のためにも、墓じまいについて真剣に検討してみてはいかがでしょうか。

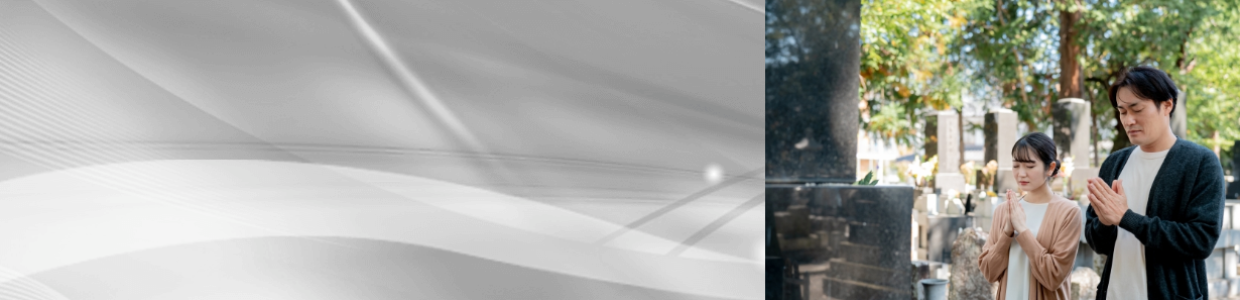







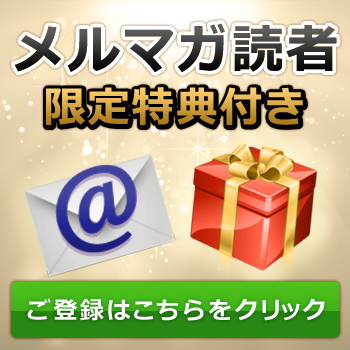
ちなみに、浄土真宗では、人は死ぬと同時に成仏して極楽浄土に送られますので、成仏できなくて祟る、ということがあり得ないのです。